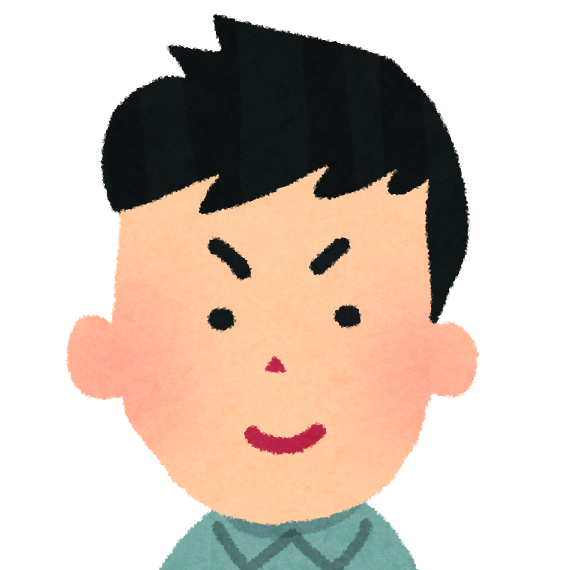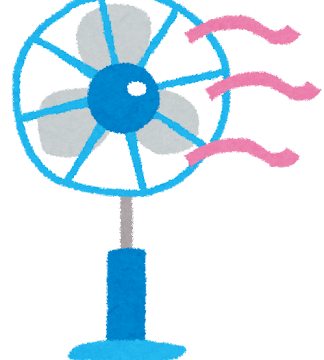生後5ヶ月の我が子も首が座り、こちらから声をかけると反応したり、コミュニケーションが取れるようになると更に楽しくなりますね。
だけど、成長とともに不安や心配事は増えていきますよね。生後5ヶ月の赤ちゃんがいるご家庭のパパ、ママはこのような不安や心配事を抱えています。
親戚や家族からも落ち着きがない子だとか、ADHD(注意欠如・多動症)の疑いがあるんじゃない?言われている。多動なの?
ADHDとは?
注意欠如・多動症(ADHD)とは、発達水準からみて不相応に注意を持続させることが困難であったり、順序立てて行動することが苦手であったり、落ち着きがない、待てない、行動の抑制が困難であるなどといった特徴が持続的に認められ、そのために日常生活に困難が起こっている状態です。12歳以前からこれらの行動特徴があり、学校、家庭、職場などの複数の場面で困難がみられる場合に診断されます。
引用:国立精神・神経医療研究センター
このような悩みをお持ちのパパさん、ママさんも多いですね。
今回は、生後5ヶ月の赤ちゃんが、「じっとしない」、「暴れる」、「落ち着きがない」など不安に思う皆さんの、その不安を解決してきたいと思います。
Contents
生後5ヶ月の赤ちゃんの特徴

生後5ヶ月となると、首がしっかりと座り、うつ伏せで上半身をしっかりとおこしたり、寝返りをする子もいます。
手の動きが活発になり、掴む力も発達して、おもちゃなどを掴もうとするようになります。
さらに、人の顔を少しずつ区別できるようになり、笑顔を見せたり、声を出すことが増えてきますね。(家族とそうでない人がわかり、特にママを特別な存在として認識するようになっているようです。)もちろんパパのことも認識していますので、落ち込まないでください。やはりママは特別です。
このような中、4ヶ月までは、黙って抱っこされていたり、横になっていてもおとなしかったりしましたが、5ヶ月くらいから、急に手足をバタバタさせたりして落ち着かなかったり、抱っこしていても反り返ったりしてじっとしていなかったり、急に奇声を発したりしてどうしたの?と思う行動が出たりします。
私の子供も実際に生後5ヶ月くらいから急にこのような行動が出て両親からも心配されました。
じっとしない・暴れる・落ち着きがない理由や原因
このように暴れたりする原因は何でしょうか。これにも下記のような理由があるんです。
- 好奇心旺盛
- 何かを伝えようとしている
- 自分意思で体を動かしたい
- 不安感を伝えている
- 環境の変化によって赤ちゃんが落ち着かなく暴れてしまう
赤ちゃんがなぜ暴れたりするのか理解しておけば、自ずと対処方法もわかって安心しますよね。
一つずつ見ていきましょう。
好奇心旺盛

赤ちゃんの特徴で紹介したように、5ヶ月の赤ちゃんは身体的に成長し、新しい能力を獲得し始める時期になります。
掴む、寝返りを打つ、物を握るなどの動作が発達するため、新しい環境や物に対して、赤ちゃんは好奇心が旺盛であり周囲の世界を探求したり新しい刺激を求めて動き回ることがあります。
何かを伝えようとしている

赤ちゃんは、身体的に成長しますが、まだまだはっきりと言葉を話すことができないため、表情や動きを通じて感情や欲求を伝えています。じっとしていないことで何かを伝えようとしていることの表れだと考えてください。
この時期から少しずつ自我が芽生えていますが、言葉を発することができないため、その分暴れたり、発狂したりしてしまうんです。
特に機嫌が悪いわけではなくても、手足をバタバタさせることがありますし、全身を使って不快な気持ちを表現していることもあります。
このように赤ちゃんが手足をバタバタさせるのは、自然のことで、ちょっとした刺激でも敏感に反応する。赤ちゃんをよく観察して顔色がおかしい、手足の動きが大きくいつもと違う様子がなければ心配しすぎなくても大丈夫です。
自分の意思で体を動かしたい

生後5ヶ月になると、自分の意思で体を動かしたいという欲求が赤ちゃんには生まれてきます。
そのため、反り返ったり、抱っこを嫌がったりします。これも赤ちゃんの意思表示であり、成長にともなってよくあることです。
不快感を伝えている

お腹が空いたり、眠かったり、おむつが濡れていたりすると、赤ちゃんは不快感を示すことがあるります。具体的には次のような時に不快感を伝えています。
- おむつがぬれている
- おなかがすいた
- ゲップできず気持ちが悪い
- 温度が合わない
- 抱っこして欲しい
環境の変化によって赤ちゃんが落ち着かなく暴れてしまう
パパ、ママを認識するようになり、人見知りも始まりまる時期のため、来客やお出かけした際に、知らない人と会うと急に奇声をあげたり、抱っこされると暴れたりすることがあります。
久しぶりに帰省した時に、おじいちゃん、おばあちゃんにも慣れずに泣いてしまって、両親は少しショックを受けていました。
こうなってしまったらどうすればいいの?
生後5ヶ月から、急にこのような行動が始まると戸惑ってしまいますね。そして、どうすればいいのかと悩みますよね。
このような場合、これをすれば良い!というような完璧な対策はありませんが、赤ちゃんの特徴など知り、心構えができることで、これも成長の過程だと知ると安心できるかと思います。
次のような対策がありますので、私の経験も踏まえてどうすればいいのか紹介していきます。
- 成長の過程であることを理解し温かく見守る
- 姿勢を変えてみる
- 不快感を解消
落ち着きがなかったり、暴れたりする原因が分かったら、ちょっとした対策で不安を解消できます。
赤ちゃんの特徴を理解し、冷静に対策することで、不安や心配を解消することができます。
成長の過程であることを理解し温かく見守る
これがいちばん大切なことになります。じっとしない、暴れる、落ち着きがない、というのはどの赤ちゃんにもあることです。年齢を重ねるごとに少しずつ落ち着いていきますので、安心してください。
このような時期も一瞬、そしてこの時期にしか経験することができません。
わが子が成長しているということを全身で感じましょう。これも成長の過程だと思えば、少し冷静になれますね。
抱っこの仕方を変えてみる

横抱きにされた状態を嫌がって泣いている可能性があります。先ほど紹介したように、自分の意思で体を動かしたい赤ちゃんは、自分が思うような体勢でないと暴れてしまいます。
このような場合、抱っこの仕方を変えてみるといいです。反り返ってしまう時は、縦抱きや前向き抱っこにしてみたり、見える景色を変えてあげることも対策の1つです。抱っこが嫌というより、横に寝かされた状態が嫌な場合があります。
我が家も、空を飛んでいるかのように抱っこしてあげたりしたら喜んでいました。
姿勢を変えてみる

寝転がらせたときに反り返るのは、寝返りをしたいからかもしれません。
仰向けに寝かせると嫌がるという場合は、寝具や着ている服の背中が不快ではないかを確認して、着替えをしたり、肌に触れるものを見直したりしましょう。
仰向けの姿勢そのものが嫌いな赤ちゃんもいます。自力で寝返りができるようになるまでは、そばで見ている必要がありますが、うつ伏せにすると安心して落ち着くこともあります。
お馬さんごっこで親の背中にうつぶせに乗せてみると、子どもは落ちないように必死につかまります。うつぶせで馬乗りすることで、反り返りを防ぐ姿勢を覚えることができます。
あぐらをかいてその上に前向きに座らせて背中を丸めたり、丸めた布団の上にうつ伏せで乗せて背中を丸める方法も効果的、この際、顔の下に玩具を置いて見せるといいです。
不快感を解消
授乳のリズムが整っていなかったりすると、お腹がすく時間が早かったりすることもありますし、オムツが蒸れていて不快感を感じている場合は、オムツをチェックしたり授乳をしたり、抱っこすると落ち着くことがあるります。
暑い、寒いなどで泣いている可能性もあるため、体温調整や室温調整をしてみるのも落ち着かせる対策のひとつです。この時、赤ちゃんの体温を測るには、手足ではなくお腹を触ってみて温かいかどうか確認してください。
まとめ
赤ちゃんの暴れたり、じっとしていなかったり、落ち着きがなかったりする時の原因とその対策を紹介してきました。
原因
好奇心旺盛
何かを伝えようとしている
自分意思で体を動かしたい
不安感を伝えている
環境の変化によって赤ちゃんが落ち着かなく暴れてしまう
対策
成長の過程であることを理解し温かく見守る
姿勢を変えてみる
不快感を解消
理由は様々だと思いますが、赤ちゃんにも意思があることを理解し、暴れたりする理由を理解することで安心感が生まれます。
また、そのような中でも赤ちゃんと触れ合うことで、次第と何を伝えたいか理解できるようになります。
泣きながら手足をバタバタさせていると、心配になってしまいますが、今の期間だけしか見られないこと。我が子の可愛い姿を目に焼き付けておきましょう。