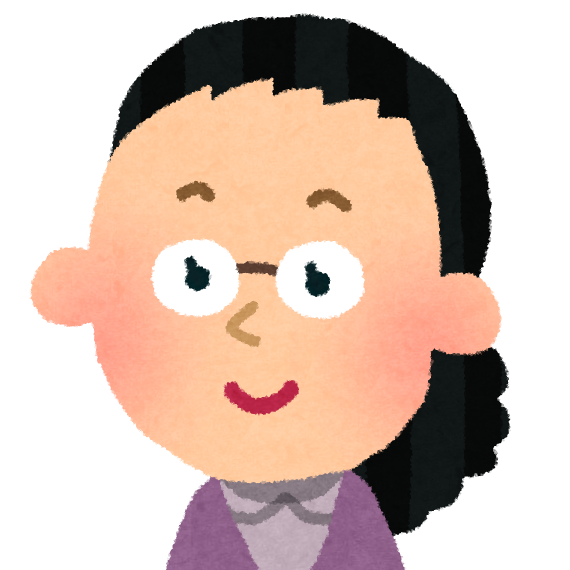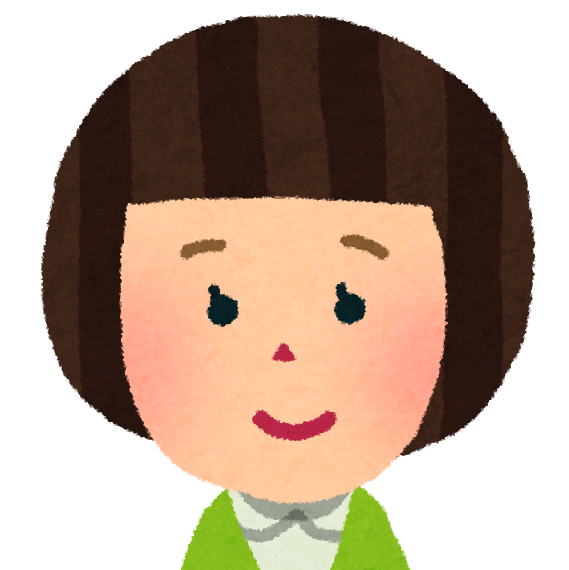生後3ヶ月になるとようやく首がすわり始め、昼と夜の区別がおおよそ付くようになってきて、夜4~5時間ほどまとまって寝るなどの変化があります。
その一方で、そのようなネットの記事や育児本などを読むと
などと不安に思ってしまいますよね。
大丈夫です!!育児書通りに育つ子なんてほぼいないです!
私は大変過ぎてこの頃の記憶は一切ありません!
ただ、3か月で混合育児から完ミ(完全ミルク)に切り替えました。
この頃の育児日記をよみがえりながら、少しでも悩んでいるママ・パパさんの手助けになれるようまとめてみました!
Contents
生後3か月のミルク・授乳の目安!

生後3ヵ月の赤ちゃんの母乳 などの授乳回数は、産まれたばかりの頃に比べると少なくなっていきます。
母乳育児の赤ちゃん、ミルク育児の赤ちゃん、混合育児の赤ちゃん。どのタイプの赤ちゃんも生後1~2か月の時期と比べて、平均で140~170グラムと1回の授乳で消化できるミルクの量が増えてくるので、授乳回数は1日6-8回ぐらいに減ってきます。
授乳間隔や回数、飲む量は個人差が大きいため、一概には言えません。
それを踏まえた上で詳しくみていきましょう。
赤ちゃんを育てるには、母乳だけを与える「完母」(完全母乳育児)、粉ミルクだけを与える「完ミ」(完全ミルク育児)、母乳と粉ミルクを併用する「混合」(混合育児)という選択肢がありますが、近年は母乳育児が推奨されることが多いです。
母乳育児の場合
- 間隔:3~4時間おき
- 回数:5~8回
上記はあくまで目安なので、これよりも多い場合や少ない場合もあります。
一般的に母乳はミルクよりも消化が早いと言われているため、特に完母(完全母乳育児)の場合は、混合育児に比べて授乳間隔が短く、回数も多くなりやすい傾向にあります。
1回の授乳にかける時間の目安は、片側10~15分程度です。
ただし、時間で区切ってしまうと、赤ちゃんがまだ飲み足りない場合もあります。
両側終えた段階でもまだぐずる場合や飲み足りなさそうにしている場合は、時間を気にせず満足するまで与えてあげましょう。
混合育児の場合
- 間隔:3~4時間おき
- 回数:5~6回
母乳育児と同じく間隔は3~4時間おきですが、混合育児の場合はミルクも併用するため、回数は若干減ります。
ミルクの消化に時間がかかる分、間隔を少し長めにとってあげても良いでしょう。
混合育児の場合は、まず母乳をあげてから足りない分をミルクで補填します。
母乳育児と同じく片側10~15分を目安にあげたら、30~40ml程度のミルクを足して様子をみます。
まだぐずったりまだ欲しそうにしたりしている場合は、再度30~40mlほどミルクをあげましょう。
この時期は母乳の量も安定してくるので、ミルクを拒否する子もいます。
その場合は、母乳の量が足りていると言えるため、無理にミルクをあげる必要はありません。
また、夜間にまとまった時間寝てもらうようにする場合は、母乳をお休みしてミルクを160~200ml与えるのがおすすめです。
消化に時間がかかる分、母乳を飲ませるときよりも長めに寝てくれるかもしれません。
【母乳のメリットとデメリット】
メリット:胃に優しく、消化しやすい。便秘にもなりにくい
デメリット:腹持ち時間が比較的短い
【ミルクのメリットとデメリット】
メリット:腹持ち時間が比較的長い
デメリット:消化しづらく、胃に負担がかかる。便秘になることもある
授乳間隔が短い理由
生後3ヶ月でも授乳間隔が短い、もしくは短くなることがあります。その場合の理由としては、下記のようなことが考えられます。
- 個性による違い
- 満腹中枢ができてくる
- ミルクの量が少ない
赤ちゃんにも個性があり、その個性が授乳間隔を短くしていることがあります。
また、生後3~4ヶ月になると満腹中枢が発達してくるので、赤ちゃんが飲みたい量しか飲まなくなります。
この場合は、吐き戻しなどに繋がるため、授乳間隔を延ばそうと無理矢理飲ませるのはやめましょう。赤ちゃんのペースで授乳を行ってあげてください。
混合育児の場合は、寝る前の授乳時はミルクだけにすると、3~4時間、長いと4~5時間まとまって寝てくれることもあります。
母乳育児の場合は搾乳器で母乳を絞り、ストックを作っておくようにしましょう。
そうすることで、ママがツラいときにパパが代わりに温めた母乳を哺乳瓶であげることもできます。
授乳間隔が短いと、それだけママ・パパの負担が増え睡眠時間や自由な時間もなくなります。我が子は可愛くても大変ですよね!
成長とともに授乳間隔は長くなっていくので、もう少しの辛抱です!
生後3か月の睡眠時間

生後3ヵ月になると、赤ちゃんの睡眠の習慣に変化が現れます。
個人差がありますが、昼間の赤ちゃんの授乳量が増え、夜の授乳量が少なくなったり、授乳が不要になったりします。
日中に起きている時間が長くなり、より活発に活動するので夜間にまとまって寝てくれる赤ちゃんもいたりと、昼と夜の区別が段々とついてくるようになります。
生後3ヵ月にもなると、昼間に2~3回ぐらいお昼寝をして、夜にはまとめて眠るようになるかもしれません。
夜に5~6時間ほどまとめて眠る赤ちゃんが増えてきますが、すべての赤ちゃんではありません。
個人差がありますが、朝はカーテンを開けて日光を取り入れて部屋を明るくし、授乳や離乳食、散歩やお風呂などの時間をある程度決めたり、夜は暗く静かにするなどして生活リズムを整えていきましょう。
赤ちゃんの睡眠とは
赤ちゃんも大人も一晩中、ずっと熟睡しているわけではなく、浅い睡眠(レム睡眠)と深い睡眠(ノンレム睡眠)を繰り返しています。
生まれたばかりの赤ちゃんは昼と夜の区別がつかず、眠りと目覚めの周期は短くて不規則。
レム睡眠とよばれる浅い眠りが半分以上を占め、3~4時間おきに目覚めながら1日に16時間ほど眠ります。
レム睡眠の時間、赤ちゃんは少しの刺激でも目を覚ましてしまいます。
でも、月齢が進むにつれて授乳の周期を中心にしたリズムができてくるので、ママやパパは心配しないでくださいね。
生後2か月頃には、夜12時から朝5時まで起きずに 眠ってくれるようになる子も出てきます。
生後4か月頃には昼夜の区別がかなりはっきりしてきて、夜は8~10時間ほどまとまって眠れるようになる赤ちゃんもいます。
生後8ヵ月頃には睡眠のリズムが大人と同じようになる赤ちゃんもいます。
生まれたばかりの赤ちゃんが夜中に何度も起きてしまう、何かの拍子にすぐに起きて泣くことは、赤ちゃんにとっては自然なことなのです。
赤ちゃんが寝てくれない時、夜泣きどうする?
夜泣きは個人差があり、乳幼児期には多く見られるもので、対応に困ることが多いかもしれません。赤ちゃんの様子に合わせて工夫をしてあげましょう。
- 生活リズムを作ってあげる
- テレビ、スマホなどを寝かしつけになるべく使わない
- 寝かしつけるときは明かりを消す
- 寝かしつけまでの流れ-入眠儀式-を決める
- 寝る前にスキンシップの時間をもつ
生活リズムを作ってあげる
朝になったらカーテンを開けて光を取り入れ、日中は活動的に過ごしましょう。
昼間に散歩に出かけ外の空気を吸って刺激を受けると、夜は疲れて早く眠ってくれるようになります。
テレビ、スマホなどを寝かしつけになるべく使わない
スマホやテレビなどの光は刺激が強く、赤ちゃんが興奮して眠れなくなると言われています。
そのため、赤ちゃんの側でスマホは使わない方が良さそうです。
ただ、眠りを誘導する音楽や環境音などの再生に使うのはよいかもしれません。
その場合は画面の光が赤ちゃんの目に入らないようにしましょう。
寝かしつけるときは明かりを消す
明かりをつけるのはお世話をする時だけにし、夜は暗くして静かな眠りやすい環境にしましょう。
日中は、自然の光や、大人の日常生活の音がする環境で過ごさせましょう。
寝かしつけまでの流れ-入眠儀式-を決める
昼夜の区別がついてくる頃から眠る時間と寝かしつけまでの流れを決めて、その流れを寝かしつけの習慣にしましょう。
夕方あたりから毎日同じ時間に、同じことを繰り返します。
この日課を繰り返すことで、赤ちゃんも寝る時間が来たことを理解しやすくなります。
お風呂の後に授乳、心が落ち着くような音楽やオルゴールの音を聞かせてから部屋を暗くする、などの行動を入眠儀式としましょう。
赤ちゃんも寝る前の流れを理解して、安心して眠ってくれるようになるでしょう。
寝る前にスキンシップの時間をもつ
寝かせつける前に少しの時間でもいいので、マッサージや背中をなでる、添い寝をして体をトントンするなど、ゆったりした時間を作りましょう。
赤ちゃんは安心して、落ち着いて眠りについてくれるでしょう。
赤ちゃんの睡眠リズムを整えることは、とても大切なことです!
しかし、睡眠リズムを整えるためには、生活リズム全般を整えていかなければうまくいきません。
ただ、これらの方法は赤ちゃんのペースもあるので、焦ってイライラしてしまうくらいなら、「就園するまでに生活リズム全体が整えば良いっかな!」と思うくらいでもいいのでしょう。
夜泣きが続くと体力的に大変になりますから、家族と相談して、ママが体を休められる時間をつくることができると良いですね。
夜起きる回数が増えたのは睡眠退行のせい?
生後3ヶ月は睡眠退行の時期だってのは何となく知ってたけど、頻繁に起きるだけじゃなくて入眠が上手くいかなくなるのも睡眠退行の一種なのか…これはたぶんそれだ…
今日はギャン泣きではないけど、とりあえず5分くらいで1回泣いちゃうんだよね。
まぁ昨日が大変だったから今日は全然いい方だ…よかた— りん︎︎☺︎3m👶🎀←41w2d (@mom_0w015) June 16, 2023
睡眠退行とは、赤ちゃんの睡眠のリズムが整ってきたと思った矢先に、急に寝つきが悪くなったり、夜起きる回数が増えるなど、赤ちゃんの睡眠が不規則な状態に戻ることをいいます。
「寝ぐずり」や「夜泣き」などが増えるのも、睡眠退行の特徴です。
乳幼児の睡眠パターンには個人差があり、睡眠退行がみられない赤ちゃんもいますが、一般的に生後3カ月頃から2歳頃までの間に6回程起こるといわれています。
睡眠退行は、身体の成長にともなう、脳の急激な発達が大きく関係していると考えられています。
とくに、手足を動かせるようになる生後3カ月頃からは、五感が発達し、様々な経験や体験を通して、赤ちゃんは毎日急激な成長を遂げています。
脳がさまざまな刺激を受けることで、睡眠のリズムにも変化が現れます。
睡眠退行は、赤ちゃんの体と脳、心の発達の節目節目で見られるのが特徴です。
赤ちゃんがなかなか寝ついてくれなかったり、夜泣きが続いたりすると、ママ・パパもイライラしたり、辛く憂鬱な気持ちになってしまうことがありますよね。
けれども、それらの変化は我が子の正常な発育の証でもあります。
睡眠退行が現れる時期や特徴をあらかじめ把握することで、育児ストレスの軽減につながるかもしれません。
ある程度の時間が経てば脳の情報処理も追いつくため「睡眠退行」も落ち着き、睡眠時間はまた少しずつ長くなっていきます。
悩んだら病院やクリニックに相談
授乳間隔や回数、睡眠時間はあくまで一般的な目安です。
そのため、目安から外れていたとしても過度に心配する必要はありません。
その子の個性だと思って、赤ちゃんのペースに合わせてあげましょう。
ただし、授乳の間隔や回数は、ママ・パパの睡眠時間と密接な関係にあります。
いつか楽になるときが来るとわかっていても、ツラいこともあるでしょう。
そんなときは我慢せずに病院やクリニックに相談することをおすすめします。
ママ・パパであれば誰もが通る道ではありますが、育児を楽しめるように早めに専門機関に相談して不安を払拭しましょう。
病院に行ったら、軽度のうつとパニック障害の診断を受け、安定剤と睡眠導入剤を処方してもらったのね。最初、安定剤は全然合わなくてすごくしんどかったけど、今合うのもらってだいぶ症状がよくなってるの。育児中の病院本当ハードル高いけど、しんどい人、本当メンタルクリニックに行ってほしい…
— ポニもえか®︎7月19.29日撮影会☺︎ (@ponymoeka) May 31, 2019
まとめ
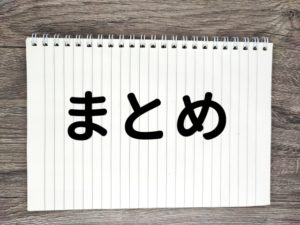
いかがだったでしょうか。
生後3か月のミルク・授乳回数、睡眠時間、夜起きる回数が増えた原因などについて見てきました。
こちらが、この記事のまとめです。
- 生後1~2か月の時期と比べ、平均で140~170グラムと1回の授乳で消化できるミルクの量が増えるので、授乳回数は1日6-8回ぐらいに減る
- 生後3ヵ月になると、2~3回程お昼寝をし夜にはまとめて眠るようになる
- 夜泣きは個人差があり、乳幼児期には多く見られるもの
- 赤ちゃんの成長にともい、不快な理由以外にも、生活リズム、睡眠リズムがまだ整っていない事や、刺激的な出来事の影響、不安な気持ちのあらわれなどが夜泣きの原因になる
- 夜泣きは「睡眠退行」が原因かもしれない
- ツラい時は我慢せずに病院やクリニックに相談する!
夜泣きが続くと本当に体力的にも精神的にも大変になります!
家族と相談して、ママが体を休められる時間をつくってあげましょう!
頑張らないことを頑張る!これ大事ですよ!