生後3ヶ月になっても、赤ちゃんが続けて10時間寝ている時、ママの頭に一番に浮かぶのは脱水にならないかの心配です。
授乳間隔が空くと「水分は足りているのか」と考えるのは当然ですし、特に子育て初心者のママは、どう対応したらいいか分からないですよね。
- 脱水かどうかを、どう見極めたらいいのか分からない
- 長い時間起きない時、授乳のタイミングを迷う
このような悩みは尽きません。
脱水の時に起こる状況がわかれば、同時に安全かどうかもわかります。まずは心配になり過ぎず、冷静に見るべきポイントをおさえることを意識しましょう!!
そうすることで、赤ちゃんからの脱水時のSOSサインをいち早くキャッチでき、ママが感じていた不安も解消されますよ。
これから脱水が疑われる時にどこを見るべきか、起こして授乳した方がいいタイミングや、体内の水分不足を防ぐための環境づくりについて紹介します。
ここでしっかり知識を増やして、落ち着いて緊急時の対応ができるようにしましょう。
Contents
【脱水が心配】生後3ヶ月の子が10時間寝る時に危険を知るための4つのチェック

10時間以上寝ていても、生後3ヶ月での睡眠はまだ個人差も大きく、問題のないケースがほとんどです。
寝過ぎでの脱水症状が気になる時は、赤ちゃんの体調に問題がないか確かめるために、確認すべき事をしっかり把握しておきましょう。
安全を確かめるための対応を知ることは、安心材料を一つでも増やすという意味でも、とても重要なことです。
息子チャン、すごく寝てる…寝過ぎ?
生後3ヶ月修正2ヶ月
ここしばらく20時~21時に寝て朝6時~7時まで起きない
ちょっと前まで5時間とか7時間で起きてたのに
10時間睡眠じゃん…脱水になっちゃうんじゃないか??
日中の睡眠が少ないのかな
親が心配でかえって寝れん— じょな (@cucQbgj28njVSOA) August 21, 2021
このように赤ちゃんは、体調が悪くても自分で合図できないので、親の方が脱水が気になって「眠れない」というパターンまで出てきています。
こんな時に赤ちゃんを守るための備えを、ママ自身がしておきたいですね。それでは、知っておきたい体調確認に必要なポイントを挙げていきます。

- 皮膚のチェック
- 顔色のチェック
- おむつチェック
- 体温のチェック
これらのチェックの中で、問題があればかかりつけ医への受診がおすすめです。
一番身近で、赤ちゃんを見守ることができる存在はママです。どこをみておくといいのかを、しっかり学んでいきましょう。
【チェック①:皮膚】脱水を知らせる一番の手がかり
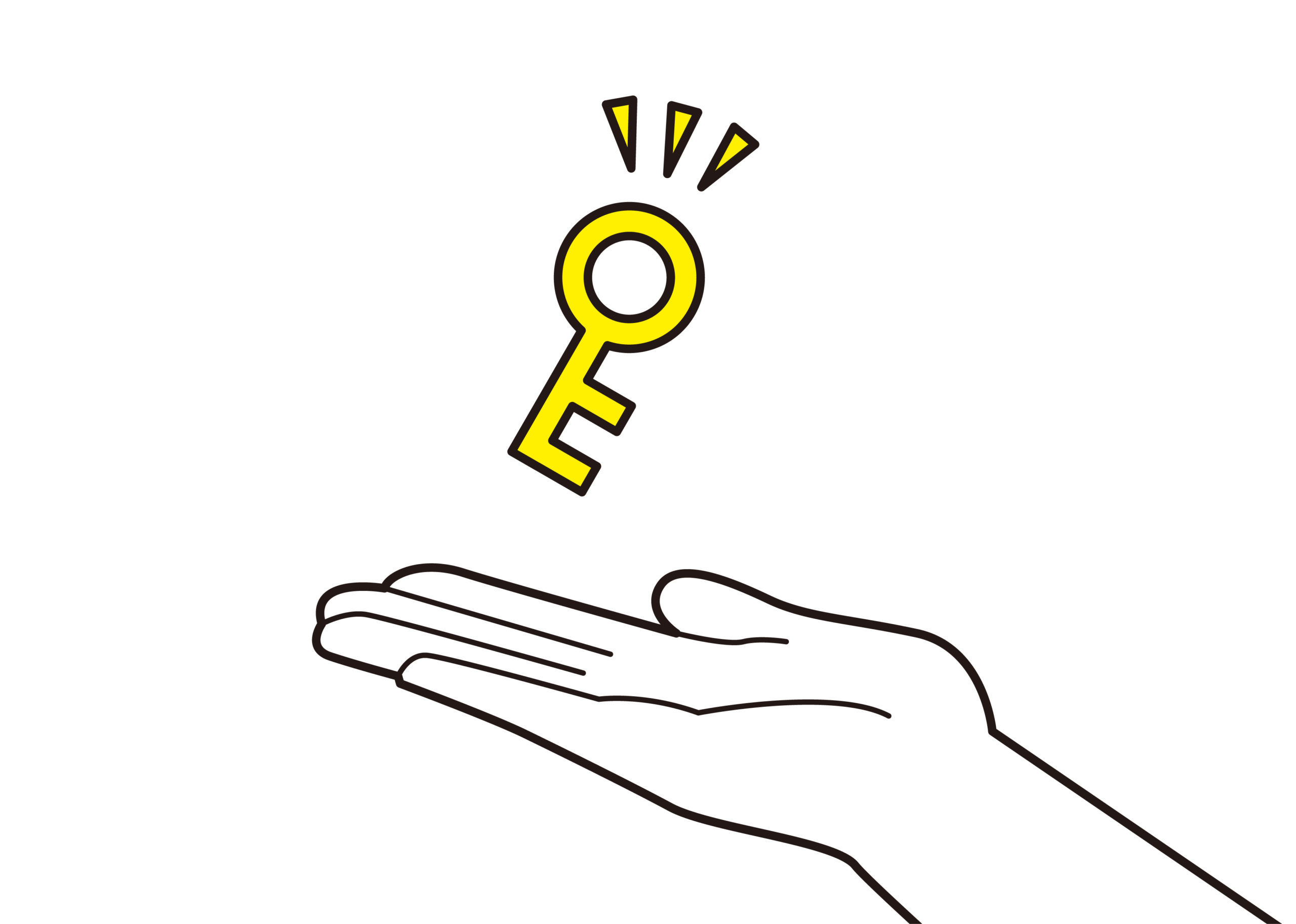
脱水症状を疑う時はまず一番に、肌を観察しましょう。
人の肌は水分を多く蓄えているので、乾燥が激しいと脱水が疑われます。特に、肌がみずみずしい赤ちゃんは、普段は大人よりも肌に多くの水分を溜めこんでいます。
赤ちゃんの体重に占める水分量は、70%〜80%もあります
通常、これだけの水分を持っている赤ちゃんだからこそ、脱水状態では明らかに様子が異なります。一つの基準として肌の状態に乾燥が見られ、ハリがないようであれば、異常と考えられるでしょう。
唇の乾燥や体の皮膚にしわがあるかを見ると、分かりやすいです
赤ちゃんは、もともと備えている水分量が多い分、乾燥やハリがなくなると目立ちやすいです。まずは、肌の観察で赤ちゃんの様子を見てあげてください。
【チェック②:顔色】見れば健康状態がわかる

赤ちゃんの顔色の確認は、すぐにできるので常に意識して行いましょう。実は、脱水症状の疑いは、顔色からわかるケースもあります。
なぜ顔色から脱水症状を予測できるのでしょうか。
脱水が起こる 血液量が減る 血圧が下がる 顔色が悪くなる
もともと脱水になる原因は、体の中にある体液が減ることで起こります。
もちろん血液も体液に含まれるので、血液が減ることで脱水になり、顔が青ざめたようにみえます。

顔色のチェックは簡単にできて、さらに赤ちゃんの体調もわかる、とても大事な作業の一つでもあるんです。
顔色が悪い、そのうえ手足も冷たい時は脱水の可能性が高いです
脱水時は、顔色が悪いと手足の血流が悪くなって冷たくなるので、あわせて意識しましょう。重症化すると、けいれんや意識障害などを引き起こすので要注意です。
元気な時の赤ちゃんの顔色を知っておくと、緊急時に素早く対応できるので、普段の生活からウォッチしておきましょう。
【チェック③:おむつ】水分量を示すバロメーター

脱水を判断する材料として、尿の状況も挙げられます。1回だけでなく、複数回にわたって尿の量が少ないということがあれば、脱水になっている可能性があります。
脱水症は、体の中の水分量が少ない状態の時に起こります。
【IN】1日に入る水分量 ≠ 【OUT】1日に出る水分量
特に赤ちゃんは、新陳代謝が活発で汗をかきやすいです。汗で出ていく水分が多くなると、体内の水分が減って、自然といつもより尿の量も少なくなります。
成長と共におしっこを貯めておくぼうこうも大きくなるので、1回あたりのおしっこの量は増え、だんだんと回数が減るのは問題がありません。
半日以上おしっこが出てなければ病院に行きましょう
いつものペースでのおむつ替えで、おしっこを全然していないorほとんどしていないという事が数回続くようなら、要注意です。
【チェック④:体温】病気かどうかを知るための目安

体の調子や病気かどうかを知るための、ヒントになってくれる体温測定は必ず行いましょう。実は、体温は脱水と深く関係があります。
私たちの体は、汗をかくこと(発汗)で体温調節をしていますが、汗で失われる水分量を補給しないと、熱の産生と放出のバランスがくずれ体温が上昇します。
つまり脱水が起きている時は、体温調節をしてくれる汗が出なくなり、しだいに熱の症状がみられる可能性があります。
実際、38度以上の熱がある場合は注意が必要です。しかし赤ちゃんは脱水以外でも、突然発熱することはよくあることです。
脱水でも緊急の時とそうでない時があるので、ポイントを見て参考にしておきましょう。
- 機嫌も良く水分が飲めていれば、診療時間を待って診察
- ぐったりしている、下痢や嘔吐などの症状があれば、救急対応
発熱時に、下痢や嘔吐があれば一度にたくさんではなく、少量の水分を何回も与えるようにしましょう。
重症化を見抜くためにも、「脱水かも」と思ったら、必ず体温を確認してくださいね。
10時間寝る時は起こす?? 生後3ヶ月の赤ちゃんの脱水を防ぐ授乳のタイミング

ぐっすり寝て授乳間隔が空いている時、赤ちゃんを起こすかどうかは一番の悩みの種です。
10時間寝ていても、基本的に日頃ミルクをしっかり飲んでいればOKです。
脱水は、体内にある水分が保てていない時に発生します。体重が順調に増えていて、普段しっかりミルクを飲んで元気であれば、ただ熟睡していることの方が多いです。

定期的に赤ちゃんの様子に気をつけていれば、寝過ぎていても基本的には問題ないので、落ち着いて見守ってあげましょう。
では実際に、脱水を未然に防ぐための授乳は、いつ必要なのでしょうか。起こすかどうか迷った時は、下の内容を基準にしてみてください。
- うなったり、寝たままぐずったりする
- おむつが濡れていない
- 脱水のチェック項目に当てはまる
まだ寝てはいるけれどうなったり、ぐずったりする時は、お腹が減って水分が欲しいサインの可能性もあります。
またおむつが濡れていない回数が1回だけなら、授乳をしてその後の様子をみましょう。

しかし、先ほど紹介した赤ちゃんの体調チェック時に、脱水が疑われる症状が確認できた時は、すぐに授乳をして病院への相談が必要となります。
しっかりと状況に合わせて、対応していきましょう。
ではここから、赤ちゃんを上手に起こして授乳する方法を紹介します。
泣かせたくない!!授乳後の不機嫌を避ける上手な起こし方

どうしても起こさないといけない場面では、静かに起こすことを徹底してください。
優しい刺激を与えてあげたり、環境を変えてあげたりすることで、赤ちゃんが無理なく目を覚ます事ができます。
赤ちゃんの上手な起こし方の例をお伝えするので、合う方法をトライしながら見つけてみてくださいね。
- カーテンを開ける、電気をつけて明かりを取り込む
- 足の裏を優しく刺激、くすぐる
- おっぱいを近づけてみる
- 布団を静かに剥がしてあげる
- おむつ交換をする
どれも優しくできる作業ばかりで、赤ちゃんを負担なく起こしてあげられます。逆に、唐突に起こすなどの行動は、赤ちゃんが泣いてしまうのでやめてあげましょう。
大きな音や、突然抱き上げてゆするのは、赤ちゃんが驚いて機嫌を損ねます
大人でも、急に起こされると目覚めが悪かったり、起きた後にスッキリしなかったりということがありますよね。
特に気持ちよく熟睡していたとしたら、赤ちゃんは不快に感じやすくなるので、気をつけて行動してあげましょう。
10時間寝るのは元気な証拠!? 生後3ヶ月の赤ちゃんの脱水を避ける環境づくり

長く寝ていても、普段の過ごし方を工夫してあげることで、夜の脱水の心配も少なくなります。
睡眠には個人差があり、眠っている間は成長に必要なホルモンが分泌されるため、睡眠自体は決して悪いことではないです。
けれども長時間寝ることで、全く脱水の心配がない訳ではないので、ママが少しでもホッとして過ごせる環境はつくっておきましょう。
- ママ自身も水分補給を意識する
- 部屋の温度・湿度に気をつける
- 赤ちゃんを感染症から守る
「寝る子は育つ」という言葉があるように、赤ちゃんにとって睡眠はとても重要です。
普段の暮らしから、脱水にならないように気を配ることで、夜中に起こして授乳しなくても済みますよ。
ぜひ、これから紹介する内容を確認して、実践してみてください。
ママ自身もしっかり水分補給を意識

母乳で育児中のママは、日頃から本人が水分を意識して補うようにしておきましょう。
赤ちゃんの水分不足は、ミルク不足とつながりがあります。そして、その母乳の量に影響を与えてしまうのが、ママの水分不足です。
母乳の80%は水分からできています
母乳はほとんど水分からできているため、赤ちゃんに与えることで、すぐにママの体はカラカラになってしまっています。
こまめに水分を補給してあげれば、そのまま赤ちゃんの脱水予防にもつながるので、普段から心がけましょう。
部屋は最適な温度と湿度を保つ

過ごしやすい温度と湿度を保つことで、赤ちゃんが水分を失わずに過ごせます。温度が高すぎると汗で、湿度が低過ぎると乾燥で水分が奪われる可能性があります。
赤ちゃんを、快適な室内環境で脱水から守って、心地よい睡眠を与えてあげましょう。
それでは季節に合った、温度と湿度を具体的に紹介します。
【季節別で見る快適な部屋環境】
| 季節 | 室温 | 湿度 | 注意点 | |
| 春(3〜5月) | 20〜25度 | 50〜60% | 昼と夜の寒暖差に注意 | |
| 夏(6〜8月) | 25〜28度 | 50%前後 | 室温の目安は外気より4〜5度低く | |
| 秋(9〜11月) | 20〜25度 | 50〜60% | 室温は20度以下にならないように | |
| 冬(12〜2月) | 20〜25度 | 60% | 感染症予防に乾燥には要注意 | |
このように季節によって、気をつけておくべき点も異なります。中でも夏場は、脱水を起こしやすい時期なので注意が必要です。
ぜひお部屋づくりから、赤ちゃんの安全とママの安心のどちらも手に入れていきましょう。
感染症にかからないように配慮

ウイルスなどの感染に気をつけることで、脱水のリスクも減らせます。一見、関係しないように見えますが、実は大きなつながりがあります。
秋から冬の寒く乾燥により、風邪、インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症による発熱、下痢、嘔吐などで体液が失われると脱水症になりやすくなります。
引用:まきた内科医院
発熱、下痢、嘔吐の症状は水分を体の外に出してしまうので、結果的に脱水になってしまう、ということも起こり得ます。
- 家族で手洗い、うがい、換気を徹底
- 湿度を保ち、乾燥を防ぐ
- ウイルスが残らないよう、部屋を清潔にする
赤ちゃんは免疫がまだ弱く、ちょっとしたことでも感染症になりやすいです。家族みんなで協力して、予防を徹底しましょう。
【まとめ】知識があれば危険は防げる!! 生後3ヶ月の赤ちゃんの脱水は10時間寝る場合でも大丈夫

今回紹介した、脱水に気づくために見るべき点を知っておくことは、ママの不安の解消と赤ちゃんの安全に直接結びつきます。
ではもう一度、赤ちゃんからの危険信号を受けとれるように、脱水が心配な時の確認点と起こして授乳すべきタイミングをおさらいしましょう!!
- 皮膚のチェック
- 顔色のチェック
- おむつチェック
- 体温のチェック
- うなったり、寝たままぐずったりする
- おむつが濡れていない
- 脱水の体調チェックに当てはまる
10時間寝ていてもまだ生後3ヶ月、月齢が低いと睡眠リズムが整わないことも多いため、起きずに眠り続けることも珍しくはないです。
万が一、脱水の可能性がある場合はどんな時か、クリアにしておけば大丈夫です。神経質になりすぎず、赤ちゃんを優しく見守ってあげましょう。







